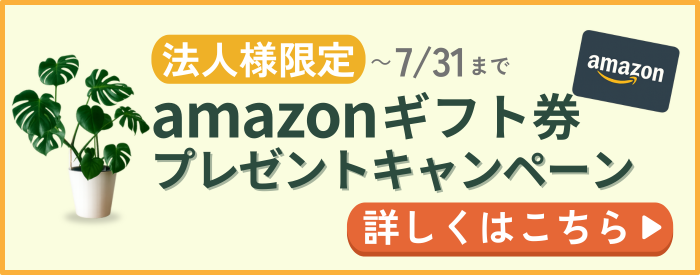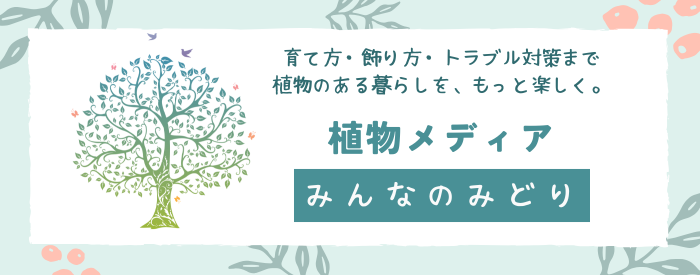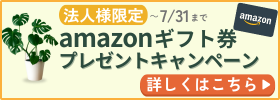#植物メディア『みんなのみどり』 に関する
記事一覧
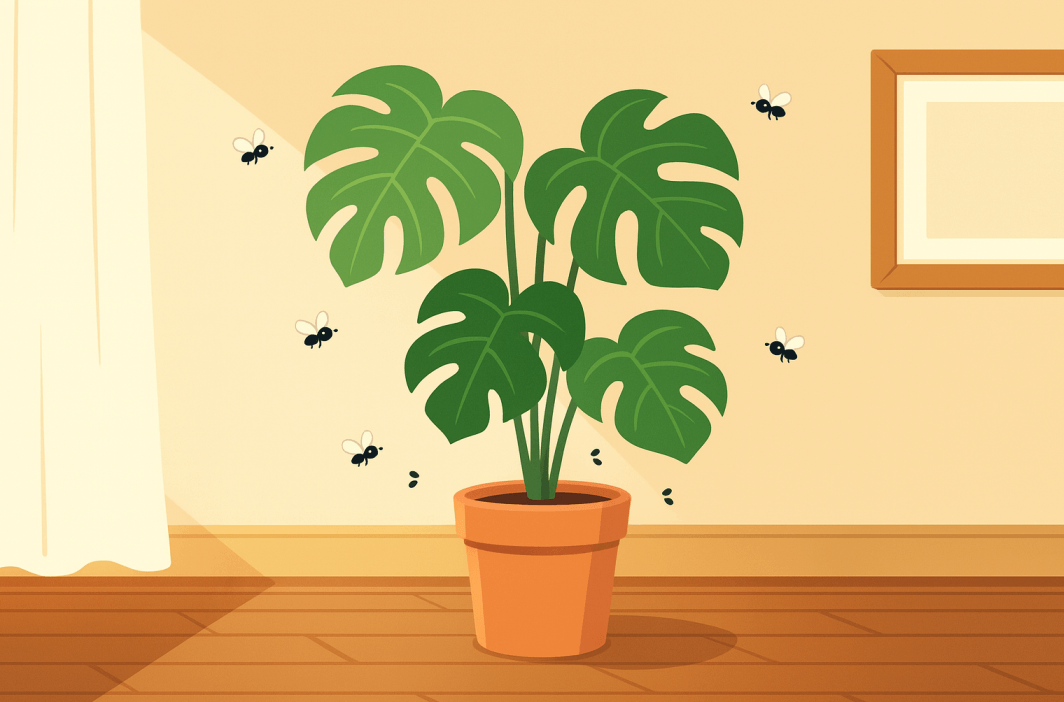
観葉植物の土からコバエが湧く理由と今すぐできる対策
室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観葉植物の土からコバエが湧く理由と、すぐにで...
公開日: 2025.07.03
最終更新日: 2025.07.03

金運を高めると言われるおすすめ観葉植物10選|置き場所や方角も
当記事では、風水において金運アップにつながるとされる観葉植物の種類や特徴、置き場所や方角などの知識を解説します。植物を通じて空間の「気」を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。
公開日: 2025.06.24
最終更新日: 2025.06.24

観葉植物の葉が黄色くなる原因と対処10個|予防法も解説
観葉植物の葉が黄色くなる原因には、水の管理不足や光量の問題、根詰まりなどさまざまな要素があります。当記事では主な原因と対策を分かりやすく解説し、植物を元気に育てるポイントを紹介します。
公開日: 2025.05.28
最終更新日: 2025.05.28

水を吸わない観葉植物の理由とは?枯れる前に確認すべきポイント
観葉植物を育てていると「水やりをしているのに元気がない」「水が土に浸透せずに流れ出てしまう」といった悩みに直面することがあります。実はこれらの問題には様々な原因が潜んでいます。 本記事では、観葉植物が水を吸わなくなる主な...
公開日: 2025.05.17
最終更新日: 2025.05.21

日光に強いおすすめ観葉植物20選|植物の特徴や育てるコツも解説
当記事では、日光に強い観葉植物の特徴や育てるコツを解説します。屋内・屋外で育てられる日光に強いおすすめの観葉植物を知りたい方も、ぜひご覧ください。
公開日: 2025.04.25
最終更新日: 2025.05.21

リビングで運気ダウン!? 風水NGな観葉植物の特徴と改善策
リビングに観葉植物を置くことは、空間に彩りと癒しをもたらす素敵な方法です。しかし風水の観点からは、すべての観葉植物が必ずしも良い影響をもたらすとは限りません。尖った葉を持つ植物や適切でない配置は、家庭の運気を下げると言わ...
公開日: 2025.04.11
最終更新日: 2025.05.21

エアコンの乾燥から観葉植物を守る!枯らさないための対策とケア
エアコンの使用で室内が乾燥すると、観葉植物は葉の変色や落葉などのダメージを受けやすくなります。特に直接風が当たる場所では、葉の水分が急速に失われ、植物の健康に深刻な影響を与えることも。 しかし、適切な湿度管理や葉水の工夫...
公開日: 2025.04.08
最終更新日: 2025.05.21

観葉植物につく白い虫の正体は何?原因と対処法・予防を解説
当記事では、観葉植物に白い虫が発生する原因と対策を分かりやすく解説します。コナカイガラムシ・コナジラミなど害虫別対処法を知り、受け皿の水や落ち葉処理など管理ポイントを押さえて、丈夫で元気な観葉植物を育てましょう。
公開日: 2025.03.24
最終更新日: 2025.05.21

観葉植物に生えた土カビの原因と対処法・予防法を解説
観葉植物に発生するカビを防ぐためには、風通しや日光の量に気をつけ、水や肥料を適切な量与える必要があります。カビの中には植物の病気につながるものもあるので注意しましょう。
公開日: 2025.03.24
最終更新日: 2025.05.21

暑さに強い観葉植物5選:初心者にも育てやすい種類
暑い夏を乗り切る頼もしい味方、耐暑性の高い観葉植物をご紹介します。初めて植物を育てる方でも安心の5種類は、強い日差しや蒸し暑さにも負けず、美しい緑を保ちます。水やりの頻度も少なくて済むため、忙しい方にもぴったり。室内の空...
公開日: 2025.03.17
最終更新日: 2025.05.21
法人のお客様には
グリーンレンタルを
無料でお試しいただけます。
『GOOD GREEN』は、全ての施設に最高のサービスを提供します。
観葉植物のレンタルが初めての方や、従来のサービスに不満がある方には、トライアル期間中無料でご利用いただけます。満足いただけない場合は料金を頂きません。植物が枯れた場合も無料で交換いたします。
ぜひ一度、プロのコーディネートを含めてお試しください。