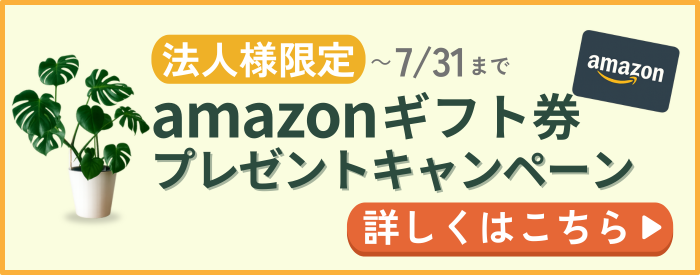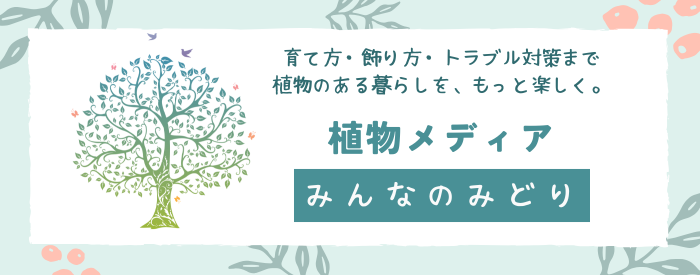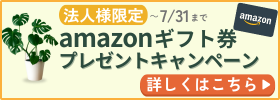観葉植物の育て方のコツ:水やり・剪定・植替えのポイントを徹底解説

おうちに1つあるだけで、グッとオシャレ感が増す観葉植物。
近年、「インテリアグリーン」という名前で注目され、園芸ショップだけでなく雑貨屋などでもオシャレな植物を見かけるようになりました。緑が部屋にあると癒される、という方も多いのではないでしょうか。
今回は、部屋をオシャレにしたい方や、購入したものの育て方がわからない方に向けて、観葉植物の育て方のコツを伝授します。
また、暑い夏は外でのガーデニングが難しくても、観葉植物なら涼しい室内でお手入れできるのでおすすめですよ♪
プランやレイアウト、
お見積りのご相談は無料!
観葉植物の育て方の基本ガイド
この記事では、水やりのコツから日当たり選びまで、観葉植物との幸せな暮らしのヒントが満載です。肥料で「お腹すいた~」のSOSに応えたり、葉水で元気をチャージしたり。エアプランツのソーキングって、まるでスパみたい!それぞれの植物の個性に合わせたケアで、お部屋の癒し空間がもっと素敵になりますよ。
水やり

観葉植物の健康的な成長には適切な水やりが不可欠です。土の状態確認から水やりの量、タイミング、方法まで、観葉植物を元気に育てるための水やりのポイントをまとめました。
1. 土の状態確認
・土の表面が乾いたら水やりのタイミング
・指で触れて土がつかない場合は水を欲している証拠
2. 水やりの量
・鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える
・表面だけを湿らせる程度の水やりは避ける
(根の成長阻害、植物の健康に悪影響を及ぼす可能性あり)
3. 水やりの場所と方法
・小さな植物:キッチンなどで鉢底から水が出るまで与える
・大きな植物:水受け皿にほんのり染み出す程度に与える
・可能な場合、ベランダや浴室でしっかり水をあげるのが理想的
4. 水やりのタイミング
・朝に行うと、日中の蒸発を利用して葉の表面を乾かし、病気予防になる
5. 適切な水やりの効果
・根の量が増え、植物の成長が促進される
・十分な水分吸収ができ、枯れにくい丈夫な植物に育つ
表面だけを湿らせる程度の水やりは避けるべきです。これは根の成長を阻害し、植物の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。根は水を求めて伸びるため、表面だけに水をやると、根が地表に向かって成長してしまいます。根の量も少なくなってしまうので、結果的に成長が悪い・水を吸える量が少なくなり枯れやすくなってしまいます。
日当たり(置き場所)

植物の性質によりたっぷり日が当たる場所、明るい日陰などの好みがあるのはご存知でしたか?
観葉植物の適切な置き場所選びは、健康的な成長のために非常に重要です。
1. 植物の種類による光の好み
・植物によって、強い日光を好むものもあれば、明るい日陰を好むものもあります。
・多くの観葉植物は明るい日陰を好みます。(レースカーテン越しに光が入る窓際、明るい室内など)
2. 情報収集の重要性
・購入時に店員から植物の光の要求について詳しく聞くことをおすすめします。
3. 適切な置き場所の効果
・植物に合った場所に置くことで、健康的で活き活きとした成長が期待できます。
・正しい光環境は、植物の長期的な健康と美しさを維持するのに役立ちます。
観葉植物は光の方向に向かって成長する性質があります。定期的に鉢を90度回転させると、バランスの取れた美しい姿に育ちます。これを「日光浴」と呼ぶ植物愛好家もいるんですよ。ちょっとした気遣いで、植物がいきいきと育つ姿を楽しめます。
肥料やり

植物は成長とともに土の栄養を吸収するため、時間経過で土中の栄養が枯渇します。栄養不足になると、植物は下葉が黄色く変色するなど、ヘルプシグナルを発します。これは植物からの「お腹すいた~」のSOSなんです!
1. 肥料の基本ポイント
・ホームセンターなどで観葉植物用の肥料を用意しておく
・固形タイプ(持続型)と液体タイプ(即効性)がある
・植物の状態や好みに合わせて選択する
2. 豆知識
・植物も「食べ過ぎ」に注意!与えすぎは根を傷める可能性あり
・説明書の量を守ることが大切
・植物の種類によって好むpHが異なる
ちょっとした配慮で、あなたの緑の友達はますますイキイキと育ちます。肥料やりを楽しみながら、植物との絆を深めていきましょう!
葉水(霧吹き)

葉水は、霧吹きを使って観葉植物の葉に直接水をかける方法です。特にモンステラなど亜熱帯原産の植物に効果的です。
・やり方
1. 霧吹きに水を入れる
2. 葉の表面がうっすらと湿る程度にスプレーする
3. 葉の裏側も忘れずに吹きかける
・メリット
1. 葉の乾燥を防ぐ
2. 埃を落とし、光合成を促進
3. 葉から水分を吸収(亜熱帯植物に特に有効)
4. 室内の湿度を上げる
葉水は通常の水やりと併用することで、より効果的に植物を育てることができます。ただし、過度な水分は病気の原因になるため、適度な量を心がけましょう。日光が当たる時間帯を避け、朝や夕方に行うのがおすすめです。
エアプランツのソーキング(水浸け)

エアプランツは特殊な水やり方法が必要な観葉植物です。以下にソーキングの方法とポイントをまとめます。
1. エアプランツについて
・亜熱帯原産の土不要の植物
・主に空気中の水分を吸収して成長
・インテリアショップでよく見かけるおしゃれな植物
2. ソーキングが必要な理由
・日本の気候では空気中の水分が不足
・原産地の湿潤な環境を再現するため
3. ソーキングの方法
・バットやボウルに水を張る
・エアプランツを水に浸す
4. 注意点
・最大6時間程度を目安に
・長時間の浸水は呼吸ができなくなるため避ける
ソーキングを行うことで、エアプランツにとってより快適な環境を作り出すことができます。定期的にこの作業を行うことで、健康的な成長を促すことができるでしょう。
失敗しない!観葉植物の剪定ガイド

観葉植物を育てていると、最初はコンパクトできれいだった姿が、だんだん伸びすぎてしまうことってありますよね。そんな時こそ、剪定のチャンスです!剪定は難しそうに見えますが、コツさえつかめば簡単にできますよ。剪定のポイントをお伝えしますね。
剪定の時期
剪定するなら、植物が元気いっぱいの5〜7月がおすすめです。この時期は成長が活発で、剪定後の回復も早いんです。それと、晴れた日を選ぶのがポイント。雨の日は湿気が多くて、切り口から雑菌が入りやすいので避けましょう。
必要な道具
剪定には、切れ味のいい剪定ばさみが欠かせません。私は植物用の専用ばさみを使っています。切り口が汚いと、病気の元となる菌が侵入しやすくなってしまいます。それと、使う前にアルコールで消毒するのを忘れずに。これだけで病気にかかってしまうリスクを減らすことができます。
剪定のやり方
まずは全体をよく見て、変な方向に伸びた枝や元気のない枝を見つけます。
枝葉が混み合っている部分も要チェック。ここを整理すると風通しが良くなって、病気や虫の被害も減りますよ。
どの植物も、枝の数が多い=栄養がそれだけ必要、ということ。剪定することで、必要な枝に栄養を成長させより元気にすることが出来る、と言われています。切るのは最初は怖いかもしれませんが、剪定は植物にとってリフレッシュになるんです。
ただし、剪定しすぎはNGです。葉がないと光合成ができなくなっちゃいますからね。適度に残すのがコツです。
固形肥料・栄養剤・活力剤の利用方法
観葉植物の育成には、固形肥料、栄養剤、活力剤の適切な利用が重要です。固形肥料には「窒素」、「リン酸」、「カリ」の三大栄養素が含まれ、それぞれ葉、花、根の成長を促進します。
肥料の袋に記載されている栄養成分比率を参考に、植物の状態に合わせて選択しましょう。
液体タイプの栄養剤は即効性があり、水やりと同時に与えられます。活力剤は微量要素を補い、植物の健康維持を助けます。これらを適切に組み合わせることで、観葉植物の健康的な成長を促すことができます。ただし、与えすぎには注意が必要です。
固形肥料

固形肥料というと白や茶色の小さな粒がおなじみですよね。実は、固形肥料には大きく分けて2種類あるんです。
1. 有機肥料
・主に堆肥など、動植物性の原料から作られます
・自然由来なので、土壌環境に優しい特徴があります
2. 化成肥料
・石灰やリン酸など、鉱石原料が中心です
・成分が安定していて、即効性があります
有機肥料は匂いが強く、カビも生えやすいんです。そのため、室内で育てる観葉植物には、多くの場合化成肥料が使われます。理由は簡単で「においが少ない」、「扱いやすい」という点などがあります。
栄養剤
液体タイプの栄養剤をご存知ですか?原液を水で薄めて使うのが一般的で、固形肥料と違って即効性があるのが魅力。水やりと一緒に与えられるので、植物がすぐに栄養を吸収できますよ。
普段は固形肥料で十分ですが、植物の調子が悪いときは液体栄養剤で素早くケア。元気を取り戻す姿を見るとホッとします。特に、水耕栽培のサボテンなど、土を使わない育て方では欠かせません。定期的に与えることで、安定した成長を促せます。
ただし、与えすぎには注意が必要。栄養剤の説明書をよく読んで適量を守りましょう。栄養剤を上手に活用すれば、植物たちがいきいきと育つ姿を楽しめますよ。皆さんもぜひ試してみてください!
活力剤
活力剤は、植物の健康維持に欠かせない”ビタミン剤”のような存在です。肥料の三大要素(窒素・リン酸・カリ)以外の微量要素を補う役割があり、植物の生育を助けてくれます。
活力剤の上手な使い方:
・肥料と併用することがポイントです。活力剤単独では栄養が不足しがちです。
・夏バテ対策や根張り促進など、植物が特別な栄養補給を必要とする時に活用しましょう。
・スプレータイプの製品なら、葉面散布が簡単にできて便利です。
私のおすすめは、植え替えの際や新芽が出る春先に活力剤を使うことです。植物の成長期に合わせて与えると、より効果的です。
最近は、有機素材を使った天然系の活力剤も増えてきました。化学物質が気になる方は、そちらを試してみるのも良いでしょう。
活力剤は魔法の薬ではありませんが、適切に使えば植物の元気をグンと引き出してくれる心強い味方です。ぜひ園芸店で色々な種類を見比べて、愛植物にぴったりの活力剤を見つけてみてください。
観葉植物の挿し木方法

観葉植物を家で増やす方法、「挿し木」(挿し芽)をご存知ですか?
植物の枝や葉を切り取り、土に挿して新しい株を育てる技術です。種から育てるイメージが強い植物ですが、多肉植物など多くの観葉植物は挿し木で簡単に増やせます。
本記事では、一般的な挿し木の手順と、特に簡単な多肉植物の挿し木方法を詳しく解説します。
一般的な挿し木の手順
観葉植物を増やす挿し木は、意外と簡単で楽しい作業です。以下の手順で、愛着のある植物をどんどん増やしていけますよ。
1. 挿し木用の枝を準備する
新しく芽吹いた、元気な枝を5cmほど斜めにカットします。枝に葉っぱがたくさんある場合は、葉っぱを半分にカットしておくと、水分の蒸発を抑えられるので成功率が上がります。
2. 枝に水分を十分に含ませる
枝に水分をいきわたらせるため、コップなどに水を張り1時間程つけておきます。活力剤の中には、発根促進作用があるものもあるので、水に混ぜておくとより効果的です。
3. 適切な土に挿す
挿し木(挿し芽)用の土やバーミキュライトなど、水分を含む土に挿します。
4. 水やりと管理を行う
たっぷり水やりをします。明るい日陰で水を切らさないようにしながら管理しましょう。1週間程でカットした枝から根が生えてきます。
5. 根の成長を待ち、植え替える
根がしっかりと張るまで待ち、その後生育用の土に植え替えるといいでしょう。
6. 土の性質に注意する
挿し木用の土は肥料分が少なく抑えてあるので、生育にはあまり向きませんのでご注意下さい。
多肉植物の挿し木方法
多肉植物の挿し木は、簡単さと高い成功率から初心者の方にもおすすめです。以下に、多肉植物を増やすコツをまとめました。
1. 葉挿しの手順
・健康な葉を親株からそっと取り外します。
・2~3日陰干しして、切り口を乾燥させます。
・用意した軽い土の上に葉を置きます。
2. 環境作り
・明るい日陰に置き、直射日光は避けましょう。
・霧吹きで土表面を軽く湿らせます(週1-2回程度)。
3. 成長の様子
・2週間ほどで根が出始めます。
・その後、小さな葉が現れ、新しい株に成長していきます。
注意点として、水のやりすぎには要注意。多肉植物は乾燥に強いので、土が乾いてから与えるのがコツです。
この方法で、一つの葉から新しい株が育つ様子を観察できるのは、植物育成の醍醐味。ぜひ挑戦してみてください。上手くいけば、あっという間に多肉植物コレクションが増えていきますよ。
観葉植物の間引きの方法

種まきから植物を育てる際、必要な作業に「間引き」というものがあります。間引きとは、たくさん生えてきた芽の中から、元気な芽を選んで残し、他の芽を抜く作業のことです。これは植物が健康に育つためにとても大切なんです。大きく育った芽を残し、弱々しいものを抜いて健康的に育ててあげましょう。
初めての方には少し難しく感じるかもしれません。でも大丈夫!簡単なステップを覚えれば、誰でも上手にできるようになりますよ。
1. 間引きのタイミング
・最初に出てくる小さな葉っぱ(双葉)の次に出てくる、本物の葉っぱ(本葉)が2~3枚生えたら間引きの時期です。成長に差が出てどの芽が元気か判断し易くなります。
2. 選び方
・双葉と本葉をよく見て、大きくて元気そうなものを残します。
・鉢の中でバランスよく配置されるよう考えて残す芽を決めます。大きく育った後の事を考えるとバランスも重要なポイントです。
3. 抜き方
・芽の根元をそっとつまみます。
・ゆっくりとまっすぐ上に引っ張ると、すると簡単に抜けます。
芽の間隔が狭いまま育つと、風通しが悪くなる・葉が重なり合って光合成がうまくできないなどの問題が起きてしまいます。また、風通しの悪さは病害虫の原因になりますので気をつけましょう。
最初は少し勇気がいるかもしれませんが、植物のためを思って優しく作業してくださいね。がんばって育てた芽を抜くのは少しさみしい気持ちになるかもしれません。でも、これは植物全体の健康のためなんです。愛情を込めて作業すれば、きっと植物も応えてくれますよ。
観葉植物の育て方の応用編
痛んだ植物を復活させる方法

大切に育てていた観葉植物が枯れてしまった…そんな経験がある方も少なくないはず。植物を枯らさないコツは、買う前にその植物の育て方を把握しておくことですが、いざ傷んでしまった場合にはどうしたらいいのか?復活の方法をまとめます。
1. 根本的な原因を特定する
・日当たり、水やり、温度など、環境要因を見直す
・病害虫の有無をチェック
2. 適切なケアで回復を促す
・弱った葉は除去し、植物の負担を軽減
・日陰で休ませ、ゆっくりと回復させる
・水やりは控えめにし、根腐れを防ぐ
3. 再生のチャンスを与える
・植物を増やすことができる挿し木は、傷んでしまった植物から新しく元気な株を作るのに有効
・一度鉢から取り出し、根っこの様子を確認。腐った根っこはブヨブヨしていたり、色が変色している
・根が腐っている場合は、健康な部分のみを残して植え替え(枝や葉などもカットし少なくすると、必要な養分が減るので復活が早くなる)
4. 栄養補給で元気づける
・液体肥料を薄めて与え、徐々に体力を回復
・霧吹きで葉に水分を補給する
植物の回復には忍耐と適切なケアが不可欠です。種類によって水分要求が異なるため、各植物に合った水やりを心がけましょう。また、環境変化には弱いので、移動する際は徐々に順応させることが大切です。
愛情を持って丁寧に世話をすれば、多くの植物は驚くべき生命力で応えてくれるはずです。諦めずに、植物との対話を楽しみながら育ててみてください。
留守中の植物の管理方法
年末年始やお盆などで長期に家を空ける時、愛着のある観葉植物たちが心配になりますよね。でも大丈夫!ちょっとした工夫で、留守中も植物たちを元気に保つことができます。
1. 水受け皿に水を張っておく
・一番簡単な方法です。水を張っておくことで下部から水が吸収され、水切れを防止してくれます。
・水受け皿のサイズも様々ですし、夏場の窓際の植物は水を必要としますので、数日程度の外出ではいいかもしれませんが、長期の不在には少し心もとないかもしれません。
2. 水やりの自動化
・500mlや2ℓのペットボトルに、100均で手に入る給水器をペットボトルに取り付けるだけで、簡単な自動給水システムの完成
・給水器付のペットボトルを土に挿しておくことで、定量が土に補給され枯れるのを防いでくれる
・給水器は普段から水やりの管理をするのにも使用できるので、1つあると便利
3. 保水力アップ
・保水剤の活用:土に混ぜるだけで水持ちが格段に良くなる。既存の鉢植えなら、表面の土に小さな穴を開けて保水剤を埋め込みましょう。一回の水やりで10日程持つようになるものもあります。
4. 事前のケア
・出発前の十分な水やり:土が十分湿っている状態にしておくことで、初期の耐久力が上がります。
・枯れ葉や弱った枝の除去:植物の体力を奪う要素を取り除いておくと、より長持ちします。
これらの方法を組み合わせることで、1週間から10日程度の不在なら、多くの観葉植物は問題なく乗り切れます。ただし、植物の種類や季節によって水分要求量が異なるため、個々の植物のニーズに応じて対策を調整する必要があります。 特に夏場は蒸発が早いので注意が必要です。
帰宅後は、たっぷりと水をあげ、葉の表面を霧吹きで湿らせてあげましょう。植物たちもきっと喜んでくれるはずです!
植物を育ててみたいけど、枯らしてしまうのが心配…そんな方におすすめなのが、GOOD GREENの植物レンタルサービスです。
カタログからお好みの植物を選べるほか、専門スタッフがお部屋に合った植物を選定します。初期費用を抑え、手軽にグリーンのある暮らしを始められますよ!
さいごに
植物は生き物なので、愛情をかけてお世話をすることが必要ですが、その分愛着も沸きます。水やり、剪定、植え替え、肥料など、様々な作業を通して発見も多いはず。育て方のコツをつかんで、素敵なグリーンライフを送ってください!
関連記事
-
観葉植物の植え替え方法・手順!時期や植え替え後の対応も解説
 観葉植物を育てているものの何年もそのままにしていたり、買ってからプラスチックのカップでそのまま育てていたりする方もいるのではないでしょうか。観葉植物は適切な時期に植え替えをしない…
観葉植物を育てているものの何年もそのままにしていたり、買ってからプラスチックのカップでそのまま育てていたりする方もいるのではないでしょうか。観葉植物は適切な時期に植え替えをしない… -
観葉植物の葉水とは?必要な理由や正しいやり方・注意点を解説
 観葉植物を生き生きと美しく育てるには、水やりの他に葉水も重要です。葉水は観葉植物の葉に水を与えるシンプルなお世話の方法の1つですが、観葉植物を育てる方の中には、なぜ葉水が必要なのか…
観葉植物を生き生きと美しく育てるには、水やりの他に葉水も重要です。葉水は観葉植物の葉に水を与えるシンプルなお世話の方法の1つですが、観葉植物を育てる方の中には、なぜ葉水が必要なのか… -
初心者でも育てやすい簡単で寿命の長い観葉植物13選
 観葉植物を育ててみたいけれど、経験がないから枯らしてしまうんじゃないかな・・世話を続けられないんじゃないかな・・と不安で手を出せずにいる方も多いのではないでしょうか。 多年草や低木…
観葉植物を育ててみたいけれど、経験がないから枯らしてしまうんじゃないかな・・世話を続けられないんじゃないかな・・と不安で手を出せずにいる方も多いのではないでしょうか。 多年草や低木… -
玄関に置いてはいけない観葉植物の特徴!風水効果で運気を上げる植物も
 当記事では、風水的に良くないとされる玄関に置いてはいけない観葉植物の特徴を解説します。玄関に置くのにおすすめの観葉植物の種類を知りたい方も、ぜひご覧ください。
当記事では、風水的に良くないとされる玄関に置いてはいけない観葉植物の特徴を解説します。玄関に置くのにおすすめの観葉植物の種類を知りたい方も、ぜひご覧ください。
新着記事
- 観葉植物の土からコバエが湧く理由と今すぐできる対策
 室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観…
室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観… - 金運を高めると言われるおすすめ観葉植物10選|置き場所や方角も
 当記事では、風水において金運アップにつながるとされる観葉植物の種類や特徴、置き場所や方角などの知識を解説します。植物を通じて空間の「気」を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。
当記事では、風水において金運アップにつながるとされる観葉植物の種類や特徴、置き場所や方角などの知識を解説します。植物を通じて空間の「気」を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。 - スマートサプライグループに「株式会社埼玉工芸」が加わりました
 〜スマートサプライグループとして、空間演出の価値をより高く、より広く〜 2025年6月吉日株式会社GOOD GREEN このたび、空間装飾の企画・施工を手がける株式会社埼玉工芸(本社:埼玉県上尾市…
〜スマートサプライグループとして、空間演出の価値をより高く、より広く〜 2025年6月吉日株式会社GOOD GREEN このたび、空間装飾の企画・施工を手がける株式会社埼玉工芸(本社:埼玉県上尾市… - 観葉植物の葉が黄色くなる原因と対処10個|予防法も解説
 観葉植物の葉が黄色くなる原因には、水の管理不足や光量の問題、根詰まりなどさまざまな要素があります。当記事では主な原因と対策を分かりやすく解説し、植物を元気に育てるポイントを紹介し…
観葉植物の葉が黄色くなる原因には、水の管理不足や光量の問題、根詰まりなどさまざまな要素があります。当記事では主な原因と対策を分かりやすく解説し、植物を元気に育てるポイントを紹介し…
法人のお客様には
グリーンレンタルを
無料でお試しいただけます。
『GOOD GREEN』は、全ての施設に最高のサービスを提供します。
観葉植物のレンタルが初めての方や、従来のサービスに不満がある方には、トライアル期間中無料でご利用いただけます。満足いただけない場合は料金を頂きません。植物が枯れた場合も無料で交換いたします。
ぜひ一度、プロのコーディネートを含めてお試しください。