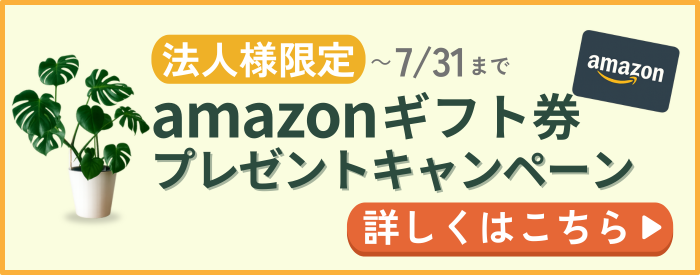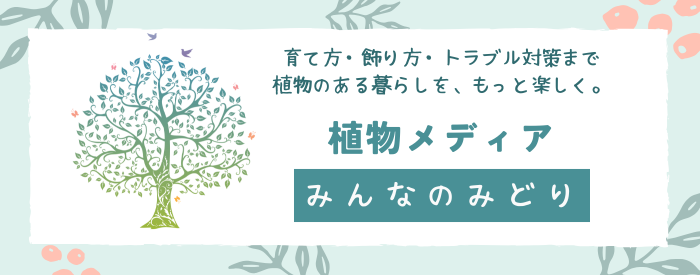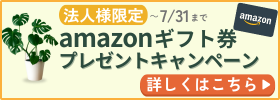観葉植物のよくある病気5選!原因と予防法・健やかに育てる方法も

観葉植物を育てると家の中に緑が広がり、部屋のイメージが一変します。リラックス効果のあるグリーンは、家に安らぎをもたらしてくれます。
ただ、観葉植物はときに病気にかかることがあります。原因が分からずに枯れてしまった経験のある方もいるのではないでしょうか。植物が枯れるには必ず原因があります。
今回は、観葉植物に発生する病気について、また病気になったときに素早く対応できるように、対策や予防法についても説明します。
プランやレイアウト、
お見積りのご相談は無料!
【目次】
2. 観葉植物に多い病気の種類と症状・対処法
1. うどん粉病
2. 炭疽病
3. 灰かび病
4. すす病
5. 軟腐病
4. 観葉植物の病気の予防法
1. 風通しの良い場所に置く
2. 剪定をする
3. 予防殺菌剤を散布する
5. さいごに
1. 観葉植物が病気になる原因

観葉植物の葉が斑入り種でもないのに白っぽくなったり、黒や灰色に変色したりしている場合は、病気にかかっている可能性があります。葉がしおれたり茎が垂れたりと元気がない様子が見られるときも、病気を疑ったほうがよいでしょう。
病気に適切に対応するためには、原因を知ることが大切です。ここでは、植物が病気にかかるおもな原因について解説します。
1-1. カビ
植物が病気になる原因としてもっとも多いのが、カビの発生です。カビは空中を浮遊しており、高温多湿など好みの環境が整うと一気に繁殖します。以下のような環境にあると植物や土にカビが生えやすくなるため、対策が必要です。
| ・何年も同じ土を使い続けている ・葉が生い茂り、風通しが悪くなっている ・風通しの悪い場所で管理している ・水をやりすぎている |
良い土は小さな土壌粒子が集まった団粒構造をしています。適度な隙間があるので水はけや空気の通りが良く、植物にとって理想的な環境です。ところが、土が古くなると団粒構造が崩れるため、だんだん通気性や排水性が悪くなり、土がじめついてカビが生えやすくなります。
上記の他、肥料の与えすぎにも注意しましょう。カビにとっても肥料は養分です。植物が弱って抵抗力が落ちた際、元気づけようとして肥料を与えすぎると、カビが繁殖しやすくなります。
1-2. 害虫

室内で観葉植物を管理していても、害虫は開けた窓から入ったり住人の荷物に付着して侵入したりしてきます。植物が弱っているときに害虫が侵入すると、一気に繁殖するので注意が必要です。
植物は以下のような環境では生育が悪くなり、害虫が発生しやすくなります。
| ・光がほとんど入らない日陰で管理している ・植物が密集している |
カビと同様、肥料のやりすぎには注意が必要です。害虫の多くは肥料に含まれる窒素を好むため、肥料過多の植物の周りは害虫が発生しやすくなります。
2. 観葉植物に多い病気の種類と症状・対処法
病気によって対処方法が異なるため、どのような病気かを見極めることが必要です。よく似た症状もありますが、じっくり観察するとそれぞれの症状に特徴があります。
症状を見ても分からない場合は、まず患部を取り除いて廃棄しましょう。早期に廃棄することで、病気の蔓延を防ぐことができます。
病気を発見したら消毒を行いますが、病気によって使用する農薬の種類が異なります。希釈倍率や使用方法は農薬のラベルに詳しく記載されてるため、確認して正しく農薬を使いましょう。
ここでは、よく発症する病気の特徴と発症時の対処法を紹介します。
2-1. うどん粉病

うどん粉病は、葉に白い粉をまぶしたような斑があらわれるのが特徴です。最初は小さな点がまだらにあらわれ、放置していると次第に白い部分の面積が広がり、葉全体が白く覆われて最終的には枯れてしまいます。
発生原因は糸状のカビです。春から秋にかけて多く発生しますが、観葉植物を室内で管理している場合は冬でも発症することがあります。
初期症状の段階であれば病変した葉を切り取って処分しましょう。全体に広がっている場合は薬剤を散布して対処します。
2-2. 炭疽病

炭疽病は、葉や茎などに茶色や灰色の円形の病斑があらわれるのが特徴です。葉に出た場合は次第に病斑が広がり、やがて穴が開いて最終的には枯れます。茎や枝に出た場合は、斑点部分から先が完全に枯れてしまいます。
発生原因はカビです。風外で管理している場合は梅雨など高温多湿の時期に発生しやすく、室内でもじめじめした環境で管理していると発生することががあります。
症状があらわれたら、早めに罹患した部分を切り落として処分しましょう。全体に広がってしまったら殺菌剤を散布して処置するか、あまりにひどいときは株全体を処分します。
2-3. 灰かび病

灰色かび病は、葉や茎、花などあらゆる部分で発症し、薄い褐色の斑があらわれるのが特徴です。進行するに従って腐敗し、灰色のカビで覆われてやがて枯れます。
原因はカビで、風に飛ばされて葉や茎の傷ついた部分、枯れた部分、花がらなどに付着し繁殖します。春先や秋の終わりに発症するケースが多く、真夏はあまり見かけません。
対処の基本は病変した部分を取り除いて処分することです。灰色かび病の原因菌は枯れた葉や花がらなどに付着するので、見つけたらすぐに取り除くことで予防や再発防止になります。
2-4. すす病

すす病は、発病すると葉や茎、実などに黒いすす状の粉があらわれる点が特徴です。放置していると葉の表面や茎全体が黒い粉で覆われるようになります。黒い粉は菌の胞子が集まったもので、ティッシュや布でぬぐうと落とせます。
原因は、害虫の排泄物です。カイガラムシやアブラムシといった害虫が植物の汁を吸った際に出す排泄物は糖分を含んでベタベタしており、葉や茎に付着します。すす病は、葉や茎についた排泄物を栄養分として病原菌が増殖した状態です。
黒い胞子はティッシュなどでこすると落とせます。被害が広範囲に広がっているときは、葉や茎を切り取って処分したほうが早いでしょう。カイガラムシやアブラムシなど植物に発生している害虫への対処も必要です。薬剤を散布するか、水をかけながら歯ブラシなどで丁寧にこすり落とすとよいでしょう。
2-5. 軟腐病

軟腐病は茎や葉、根などが急に腐り出す病気で、地際部分から強い悪臭を放つのが特徴です。元気だった植物が突然弱り、強い悪臭を漂わせるようになったときは、軟腐病の可能性が高いと言えます。
細菌が葉や茎などの傷ついた部分から侵入することで発病します。軟腐病にかからないためには、傷口をつくらないようにすることが大切です。食害する害虫に気づいたらすぐに駆除しましょう。花がら摘みや剪定は、傷口がすぐに乾くように天気の良い日に行います。
軟腐病には、薬剤はあまり効きません。そのため、罹患した株は抜いてすぐに処分します。菌は雑草の根の周りにいることが多いため、大切な植物の周辺に雑草が生えたときは、こまめに抜き取りましょう。
3. 病気の要因となる観葉植物が弱る原因
室内のインテリアとして観葉植物を取り入れたのに、植物に枯れた部分や黒斑が現れると心配になるでしょう。うまく管理してきれいな状態をキープし、グリーンライフを楽しみたいものです。
基本的に植物の病気は、植物が弱っているときに発生します。植物が弱る原因としてまず考えられるのは、冷暖房による乾燥です。観葉植物は湿度の高い場所を好みます。乾燥気味の状態で冷暖房の風が直接当たる場所に観葉植物を置いていると、植物が弱り葉が枯れてしまうことがあります。
水のやりすぎも植物が弱る原因の一つです。水のやりすぎで根が腐ると養分や水分が全体に行き渡らなくなり、植物が弱って最悪の場合枯れてしまいます。
また太陽の光の強さにも注意が必要です。自然にある多くの観葉植物は大きな木の下で木漏れ日ほどの光の下で自生しているため、直射日光が強すぎると葉が焼けてしまう場合があります。植物によって生きやすい環境を整えれば、植物が弱らないだけでなく、発病の予防にもつなげられるでしょう。
4. 観葉植物の病気の予防法

観葉植物の病気の予防には農薬を使うこともできますが、人の出入りする室内で育てる観葉植物に、あまり農薬は使いたくないものです。出来る限り植物の生育環境を整えて、病気にかかりにくい丈夫な植物体を育てることで、農薬に頼ることなく病気を予防できます。
ここでは、観葉植物の病気の予防法について解説します。
4-1. 風通しの良い場所に置く
カビや害虫は高温多湿な環境を好む場合が多いため、植物は日当たりと風通しの良い場所で管理するのが基本です。風が通れば蒸れが抑えられ、病害虫などのトラブル予防につながります。
観葉植物を室内で育てる場合は、部屋の中でも空気の流れがある場所に置くとよいでしょう。あまり空気の動きが発生しない場所で管理する場合は、適度に窓を開けて換気するなど対策してください。卓上ファンやサーキュレーターを使って、空気の動きをつくるのもおすすめです。
植物同士を密集させて置くのも、空気の流れをとめるためよくありません。複数の観葉植物を育てるときは、適切な間隔を空けて配置しましょう。
4-2. 剪定をする
観葉植物が元気に生長して葉が生い茂ってきたら、適度に剪定して風通しを確保しましょう。葉が茂ったままにすると、植物の内側に熱や湿気がこもって高温多湿になります。地上部が重くなりすぎて鉢とのバランスが崩れ、倒れることもあるでしょう。観葉植物を安全に楽しむためにも、適切な剪定は欠かせません。
剪定の適期は、多くの観葉植物で生育期にあたる4~5月ごろです。生育期はよく生長するので、剪定してもダメージから早く回復できます。梅雨前に葉を落としてすっきりさせることで、長雨による蒸れも防げます。ただし、観葉植物によって適した時期は異なるので、念のため剪定前に確認してください。
太い枝や茎などを切ったときは、細菌の侵入を防ぐため、切り口に癒合剤を塗ってお手入れしておきましょう。また、枯れた葉や傷んだ葉などは発見次第、時期に関係なくこまめにカットして取り除いてください。放置しているとカビや害虫を招く要因になります。
4-3. 予防殺菌剤を散布する
植物栽培では、カビや害虫が発生しないように予防殺菌剤を散布するのも効果的な方法です。枯れた枝や葉をきれいに取り除いてから、葉裏も含めて観葉植物全体に散布しましょう。年に1度だけでなく、春や梅雨時期、秋などのタイミングで定期的に散布すると、予防効果が高まります。
ただし、薬剤によって適切な散布間隔は異なります。散布しすぎると観葉植物を傷めることにつながるので、商品の説明をしっかり読んで従ってください。
また、室内で観葉植物を管理している場合は、いったん外に出してから予防殺菌剤を散布し、乾いてから取り込みましょう。薬剤が人やペットなどにかからないように十分注意してください。
植物を育ててみたいけど、病気になってしまうのが心配…そんな方におすすめなのが、GOOD GREENの植物レンタルサービスです。
カタログからお好みの植物を選べるほか、専門スタッフがお部屋に合った植物を選定します。初期費用を抑え、手軽にグリーンのある暮らしを始められますよ!
さいごに
観葉植物の病気対策は早期発見と早期対処が基本です。自生地に似た環境を整えることで、強い植物を育てられます。
病気の兆候がある場合は、農薬で殺菌・消毒し、丁寧に散布して広がりを抑えましょう。予防薬と治療薬を適切に使い分けることも重要です。
これらの対処法を理解し、実践することで、美しいグリーンに囲まれた生活を楽しむことができます。
関連記事
-
観葉植物の葉水とは?必要な理由や正しいやり方・注意点を解説
 観葉植物を生き生きと美しく育てるには、水やりの他に葉水も重要です。葉水は観葉植物の葉に水を与えるシンプルなお世話の方法の1つですが、観葉植物を育てる方の中には、なぜ葉水が必要なのか…
観葉植物を生き生きと美しく育てるには、水やりの他に葉水も重要です。葉水は観葉植物の葉に水を与えるシンプルなお世話の方法の1つですが、観葉植物を育てる方の中には、なぜ葉水が必要なのか… -
観葉植物のよくある病気5選!原因と予防法・健やかに育てる方法も
 観葉植物はときに病気にかかり、放置していると病気が進行して枯れてしまう原因になります。当記事では、観葉植物によく発生する病気5つの発症原因と対策法、また病気の予防法を解説します。
観葉植物はときに病気にかかり、放置していると病気が進行して枯れてしまう原因になります。当記事では、観葉植物によく発生する病気5つの発症原因と対策法、また病気の予防法を解説します。 -
エアコンの乾燥から観葉植物を守る!枯らさないための対策とケア
 エアコンの使用で室内が乾燥すると、観葉植物は葉の変色や落葉などのダメージを受けやすくなります。特に直接風が当たる場所では、葉の水分が急速に失われ、植物の健康に深刻な影響を与えるこ…
エアコンの使用で室内が乾燥すると、観葉植物は葉の変色や落葉などのダメージを受けやすくなります。特に直接風が当たる場所では、葉の水分が急速に失われ、植物の健康に深刻な影響を与えるこ… -
屋外で観葉植物を育てよう!メリットや育てるコツ・注意点を解説
 当記事では、屋外で育てるメリットや育てるコツ・注意点のほか、屋外で育てるのに向いているおすすめの観葉植物を種類別に紹介します。観葉植物には興味があるものの、屋内で育てるのに抵抗が…
当記事では、屋外で育てるメリットや育てるコツ・注意点のほか、屋外で育てるのに向いているおすすめの観葉植物を種類別に紹介します。観葉植物には興味があるものの、屋内で育てるのに抵抗が…
新着記事
- 観葉植物の土からコバエが湧く理由と今すぐできる対策
 室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観…
室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観… - 金運を高めると言われるおすすめ観葉植物10選|置き場所や方角も
 当記事では、風水において金運アップにつながるとされる観葉植物の種類や特徴、置き場所や方角などの知識を解説します。植物を通じて空間の「気」を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。
当記事では、風水において金運アップにつながるとされる観葉植物の種類や特徴、置き場所や方角などの知識を解説します。植物を通じて空間の「気」を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。 - スマートサプライグループに「株式会社埼玉工芸」が加わりました
 〜スマートサプライグループとして、空間演出の価値をより高く、より広く〜 2025年6月吉日株式会社GOOD GREEN このたび、空間装飾の企画・施工を手がける株式会社埼玉工芸(本社:埼玉県上尾市…
〜スマートサプライグループとして、空間演出の価値をより高く、より広く〜 2025年6月吉日株式会社GOOD GREEN このたび、空間装飾の企画・施工を手がける株式会社埼玉工芸(本社:埼玉県上尾市… - 観葉植物の葉が黄色くなる原因と対処10個|予防法も解説
 観葉植物の葉が黄色くなる原因には、水の管理不足や光量の問題、根詰まりなどさまざまな要素があります。当記事では主な原因と対策を分かりやすく解説し、植物を元気に育てるポイントを紹介し…
観葉植物の葉が黄色くなる原因には、水の管理不足や光量の問題、根詰まりなどさまざまな要素があります。当記事では主な原因と対策を分かりやすく解説し、植物を元気に育てるポイントを紹介し…
法人のお客様には
グリーンレンタルを
無料でお試しいただけます。
『GOOD GREEN』は、全ての施設に最高のサービスを提供します。
観葉植物のレンタルが初めての方や、従来のサービスに不満がある方には、トライアル期間中無料でご利用いただけます。満足いただけない場合は料金を頂きません。植物が枯れた場合も無料で交換いたします。
ぜひ一度、プロのコーディネートを含めてお試しください。