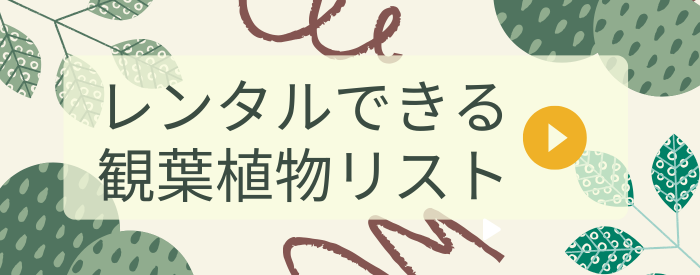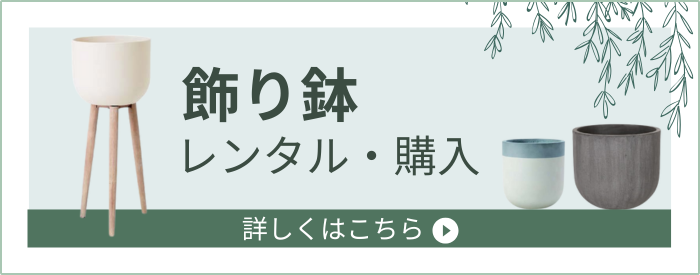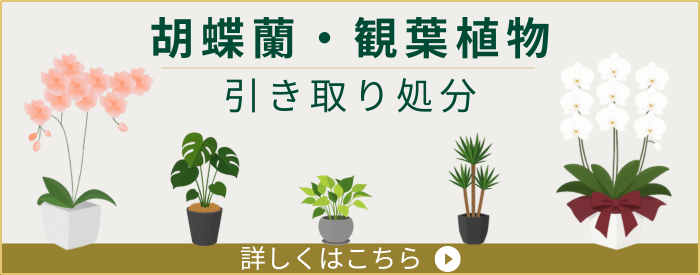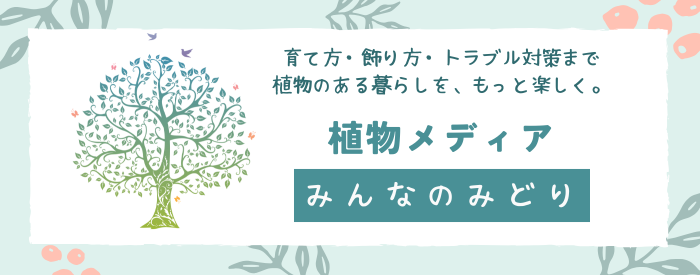観葉植物は冬にお休みモードへ。休眠期の正しい向き合い方

冬になると、それまで元気に伸びていた観葉植物の動きがゆっくりになり、葉のハリが弱くなったり水の減りが遅くなったりします。その変化を目にすると「枯れてしまうのではないか」「水が足りないのでは」と不安になる方が多く、暖房の部屋で育ててよいのか迷われる方もいると思います。
私自身も園芸を始めたばかりの頃、モンステラを寒い玄関に置き続けてしまい、冬の冷え込みに耐えられず、しおれさせてしまった経験があります。休眠期は植物の動きがゆっくりになるため、こうした急な低温ダメージを受けやすくなります。この“冬の体の仕組み”を知っておくと、季節ごとの管理が驚くほど楽になります。
目次
観葉植物の休眠とは?(仕組み・種類・休む理由)

観葉植物が冬にぐっと動きを落とすのは、弱っているからではなく「体力を守るための休眠モード」に入っているためです。気温が下がると根の働きや代謝がゆるやかになり、光や水を使いすぎないよう植物自らペースを落とします。
これは春に再び元気に育つための準備段階で、ほとんどの観葉植物に見られる自然な反応です。休眠の仕組みを知っておくと、冬の変化に落ち着いて対応できるようになります。
休眠とはどんな状態か
観葉植物の休眠とは、生命活動を最小限に抑えてエネルギーを節約する状態のことです。多くの観葉植物は熱帯や亜熱帯が原産で、寒い環境が苦手です。
気温が下がる冬は根の吸収力も弱まり、光量も不足しやすくなるため、多くの植物が自ら成長をゆるめて静かに過ごします。完全に止まっているわけではなく、必要な機能だけを残しながら“春まで休む準備”をしているイメージです。
休眠しやすい種類と特徴
| 種類 | 休眠の強さ | 特徴 |
|---|---|---|
| サンスベリア | 強い | 冬はほぼ完全に停止 |
| パキラ | 中程度 | 落葉はしにくいが寒さで葉が垂れる |
| モンステラ | 弱め | 暖かければゆっくり成長を続ける |
種類によって休眠の度合いは異なりますので、育てている植物に合わせた調整が必要です。
なぜ休眠が必要なのか
冬は光量が少なく、気温も低く、土の中の温度も下がります。こうした環境で無理に成長しようとすると、光不足による葉焼け、浸かりすぎによる根腐れなどのトラブルが起こりやすくなります。そのため植物は省エネモードに入り、自らを守るための休眠に入るのです。
<関連記事>
観葉植物の葉が落ちるのはSOSサインを詳しく解説
冬に元気がなく見える原因

冬になると、多くの観葉植物は夏のような勢いが一気に消え、どこか静かで動きの少ない姿になります。突然葉がしんなりしたり、色がくすんだように見えたり、土がいつまでも湿っているなど、普段とは違う様子に不安を覚える方も多いと思います。しかし、こうした変化には必ず理由があります。
冬の室内環境が植物にとってどのように影響しているかを知っていただくと、落ち着いて対処できるようになります。
温度の低下が植物の動きを止めてしまう
観葉植物は暖かい地域の出身で、10℃を下回ると体の働きそのものがゆっくりになります。昼間は暖房で快適でも、夜になると気温がグッと下がり、植物はその落差にストレスを感じます。
特に窓際は早朝に冷え込むため、葉がしおれたり、成長点(新芽)が動かなくなったりします。これは植物が弱っているのではなく、「今は動かないほうが安全だ」と判断している状態です。
湿度不足が葉の乾燥を招く
冬の暖房は人間にとって心地よいものですが、植物にとっては乾燥の原因になります。湿度が30%前後まで下がると、葉の水分が奪われやすく、先端が茶色く変色したり、葉全体がパリっと硬くなることがあります。
植物は呼吸をするために葉の表面に小さな穴(気孔)を持っていますが、空気が乾くとそこから水分が失われやすくなり、疲れたような姿に見えてしまうのです。
冬の光不足で葉の色がくすむ
冬の光はやさしい一方で、量が圧倒的に足りません。夏と比べると日照時間は半分程度になり、室内に届く明るさも弱くなります。
光合成が十分にできないと、葉の色が薄くなったり、濃い緑の葉でも少し元気がないようなトーンに変わることがあります。窓際に置いていても、冬は想像以上に暗いため、動きが止まって見えるのは自然な反応です。
根が冷えて水を吸えない状態になっている
植物の根は「適温」でこそ、水をしっかり吸うことができますが、冬は土が冷え込み、根の働きがゆるやかになります。すると、普段なら1〜2日で軽くなる鉢が、冬は1週間以上重いままです。初心者の方はこれを「乾いていないからもっと待つべきなのか」「でも元気がないから水を足したほうが良いのか」と迷ってしまいます。
実際には、吸う力が弱いだけで、水が不足しているわけではありません。冬の“乾かない土”は、多くの場合で正常な状態なのです。
冬の管理ポイント

冬の観葉植物は、気温・光・湿度のすべてが育てにくい方向に働きます。そのため、この時期は「普段どおりにお世話する」のではなく、植物の動きに合わせて“冬仕様”へ切り替える必要があります。ここでは、初心者でも迷わず実践できる冬の管理ポイントを、わかりやすく整理してお伝えします。
温度管理:10℃を境界線として考える
観葉植物にとって冬の一番の敵は「冷え」です。特に夜間〜早朝の温度低下は見落としがちで、日中は暖かくても朝になると葉がしぼんでいた、というのはよくあるトラブルです。室温が下がりやすい窓辺や玄関は、冬は思っている以上に冷えています。
植物は気温が10℃を下回ると代謝が落ち、根の働きも弱まり、葉にハリがなくなることがあります。ですので、冬はなるべく 「10℃以上の環境をキープする」 ことを目安にしてください。
水やり:普段の半分の量・タイミングで十分
冬の水やりは、年間を通して最も失敗が起きやすいポイントです。理由は、土が乾きにくくなる一方で、見た目の変化が少ないため「足りているのかどうか」が分かりにくくなるからです。
冬は根が冷えて水を吸う力が大幅に下がります。そのため、いつもどおりの量を与えてしまうと、鉢の中がずっと湿った状態になり根腐れを招きます。
置き場所:暖かくて明るい、しかし風が当たらない場所
置き場所は冬の管理において最も効果が出やすいポイントです。理想は、「明るい × 適度に暖かい × 風が当たらない」という3つを同時に満たす環境です。
冬は光が不足しがちなので、できるだけ自然光が入る位置に置いていただくと、葉色や植物の動きが安定します。ただし、暖房の風が直接当たる場所は避けてください。風にさらされると葉が乾燥しすぎ、先端が黒くなる原因になります。
また、夜間だけ寒い場合は「昼と夜で場所を変える」ことも効果的です。慣れるまでは手間に感じるかもしれませんが、植物の調子が大きく変わるため実感しやすい対策です。
湿度:40%前後を目安に“やさしく補う”
冬の暖房で最も変化するのが湿度です。湿度が30%以下になると、葉先が茶色くなる、全体的にパリッと乾く、という症状が現れます。これを放置すると、徐々に葉の寿命が短くなることがあります。霧吹きも効果的ですが、毎日たっぷりやると逆にカビの原因になるため、乾燥している日だけ軽く行う程度で大丈夫です。
休眠期にやってはいけない行動

植物が冬に休眠へ入る理由は「自分を守るため」です。
そのため、普段の季節なら問題なくできることでも、冬に行うと想像以上に負担が大きくなります。
ここでは 冬だけは絶対に避けたい行動 を、理由とともに詳しくお伝えします。
植え替えを行うこと
植え替えは根が一番ダメージを受ける作業です。
根の動きが止まっている冬に土を崩したり鉢を替えたりすると、植物は“防御力ゼロ”の状態で大きな刺激を受けることになります。
休眠期は根がほとんど活動していないため、新しい土へ根を伸ばす力も弱く、植え替え直後にしおれたり葉が変色することが珍しくありません。
また、「乾きにくい冬の土」、「根の吸収力が弱い状態」が重なると、少しの水分量でも根腐れを引き起こしやすくなります。植え替えは必ず 春〜初夏(植物が本格的に動き始めてから) に行うのが最も安全です。
肥料を与えること
冬は植物の吸収力が大きく落ちるため、肥料を与えても期待したような効果は出ません。
むしろ、吸収できなかった肥料成分が土の中に残り続け、「根が焼ける」、「土中のバランスが崩れる」、「カビが発生しやすくなる」といったトラブルの原因になります。
私自身、園芸を始めた頃に「元気がないなら肥料でパワーを足せばいい」と勘違いし、冬に液肥を与えてしまったことがあります。結果、根が弱っていたため吸収できず、翌週には葉が黄色くなり、回復に何ヵ月もかかりました。
冬は無理に元気を出させようとせず、肥料は完全にストップしたほうが植物にとっては安心です。
暖房で過剰に暖めること
暖房の風は、人が感じる以上に植物へ影響します。直接風が当たると、葉が短時間で乾燥し、フチが黒くなったり、葉先が丸まってしまうことがあります。
また、暖房が止まった瞬間に室温は急に下がるため、「暖かい → 急に冷たい」という温度差が短時間に繰り返され、葉と根の両方に負担がかかります。
暖房のある部屋で育てること自体は悪くありませんが、「風が当たらない位置に置く」、「暖房機から1〜2mほど離す」この2点を意識するだけで、葉のダメージは大幅に減らせます。
<関連記事>
観葉植物に生えた土カビの原因と対処法・予防法を解説
冬にこうなる…を防ぐためのリアル体験集

冬の観葉植物のトラブルは、経験豊富な人でも一度は通る道です。
植物は声を出してくれないため、少しのサインを見逃すと気づかないうちに調子を崩してしまうことがあります。
ここでは、私自身の失敗と、現場で多かったケースをもとに “なぜ起こるのか・どう改善するか” を詳しくお伝えします。
私の失敗:玄関で冷えたパキラ
園芸を始めた頃、私はパキラを玄関に置いていました。冬のある朝、葉が一気に垂れてしまい、触ると普段より明らかにひんやりしていました。夜の冷え込みで葉や茎まで温度が下がってしまったのが原因です。
改善策として、暖かい部屋へ移し、水やりを控えて様子を見ると、春には新しい芽が出てくれました。冬は、見た目以上に「温度差」が大きな負担になることを実感した出来事です。
水のやりすぎで根腐れしたケース(最も多い失敗)
冬は鉢が乾きにくく、初心者の方ほど「水が足りない」と勘違いしやすいです。実際には根が冷えて吸っていないだけで、水を足すほど悪化します。
改善策として、鉢を持ち上げて重さで判断し、軽くなるまで絶対に水を与えないこと。この感覚をつかむだけで、冬の根腐れはほとんど防げます。
光不足で弱ったモンステラ
冬の室内は想像以上に暗く、夏は十分だった場所でも光が足りなくなります。そのため葉の色が薄くなったり、下葉が黄色くなることが増えます。光合成がうまくできないことで “元気がないように見える” のは冬の典型的な変化です。
改善には、午前中の明るい場所へ数時間移動させるのが効果的です。冬の朝の光は柔らかく、植物が負担なく光合成できるため、短時間でも葉色が戻りやすくなります。
冬の失敗は誰にでもありますが、ほとんどは置き場所・水やり・光量の調整で改善できます。冬を無事に越せた植物は、春に一気に勢いを取り戻します。大切なのは“原因を知ること”です。それだけで次の冬は驚くほど楽になります。
冬越しでつまずきやすいポイントQ&A

Q1. 葉が落ちていますが問題でしょうか?
A: 冬に葉が落ちる現象には、自然な場合と注意が必要な場合があります。ゆっくりと下葉から黄色く変化して落ちる場合は、植物が古い葉を整理しているだけです。
一方で、一晩で大量に落ちる、葉が黒くなる、同時に土が乾かず幹が柔らかくなるといった状況がある場合は、根腐れや急激な温度変化が原因である可能性が高いです。土の状態や最近の置き場所の変化を振り返ると判断しやすくなります。
Q2. 暖房の部屋で乾燥が心配ですが、置いても大丈夫ですか?
A: 暖房のある部屋は温度が安定して植物には良い環境ですが、直接風が当たると葉が急激に乾燥し、先端が黒くなることがあります。風が当たらない位置に置けば暖房の部屋でも安全に育てられます。
また、湿度が40〜50%ほど保てれば、葉の乾燥は大幅に抑えることができます。加湿器を使う場合は植物に近づけすぎない位置が安心です。
Q3. 土がほとんど乾きません。水をあげるべきでしょうか?
A: 冬に土が乾かないのは根の活動が弱まっているためで、基本的には問題ありません。しかし、土が湿ったまま長期間変化しない場合や、表面にカビが出たり嫌な匂いがする場合は、根腐れの兆候です。
その場合は、暖かい場所へ移動し、数日〜1週間ほど水やりを完全に止めて根の負担を軽減することが必要です。
Q4. 冬でも日光浴はさせたほうがよいですか?
A: 冬でも短時間の日光浴は効果的です。特に午前中の柔らかい光は植物にとって負担が少なく、光合成を助けてくれます。曇りの日であっても外の明るさは室内より強いので、窓際で数時間過ごすだけでも葉の色やハリが変わります。ただし、寒さが厳しい日や直射日光が強い日には、レースカーテン越しが安全です。
Q5. 加湿器はどこに置くと良いのでしょうか?
A: 加湿器は植物から近すぎると結露やカビの原因になり、離しすぎると効果が薄まります。最も適切なのは、植物から50cm〜1m程度離した場所です。この距離であれば湿度を優しく補いながら、過剰な湿気によるトラブルを避けることができます。
植物を育ててみたいけど、日々の手入れが心配…そんな方におすすめなのが、GOOD GREENの植物レンタルサービスです。
カタログからお好みの植物を選べるほか、専門スタッフがお部屋に合った植物を選定します。初期費用を抑えて快適な暮らしを手軽に始めてみませんか?
SUBSCRIPTION


累計3,000社以上が導入、月間5,000鉢レンタル中!
GOOD GREENの観葉植物レンタルは、1鉢から始められる月額サービスです。
プランに応じて、設置や水やり、剪定、交換まで、プロにお任せOK。
日常の空間から特別なシーンまで、グリーンのある心地よい空間を手軽に楽しめます。
まずはお気軽にご相談ください。
空間の雰囲気に合わせて、最適な植物を選べます
レンタルできる観葉植物一覧はこちら
冬を越えるために植物が教えてくれること【まとめ】

観葉植物にとって冬は、活動を抑えて体力を守る大切な季節です。葉があまり動かなくなったり、土が乾きにくくなったりするのは自然な反応であり、多くの場合は心配する必要がありません。
私自身も冬の管理で何度も失敗を経験し、そのたびに植物がいかに環境を敏感に読み取って生きているかを学びました。冬は少し控えめな管理を心がけ、植物のペースに合わせて静かに見守ることで、春には再び力強く成長を再開します。冬の不安が少しでも和らぎ、安心して植物と向き合っていただければ幸いです。
関連記事
-
観葉植物はコミュニケーションの活性化に効果的!レイアウトのコツも
 オフィスに観葉植物を取り入れることで、社員同士の会話が増え、職場の雰囲気が和らぐなど、人間関係の改善が期待できます。観葉植物を導入するポイントや便利なレンタルサービスも紹介します。
オフィスに観葉植物を取り入れることで、社員同士の会話が増え、職場の雰囲気が和らぐなど、人間関係の改善が期待できます。観葉植物を導入するポイントや便利なレンタルサービスも紹介します。 -
【保存版】ハダニ予防と駆除の完全ガイド|観葉植物を守る方法
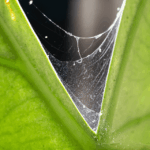 観葉植物や庭木の葉に白い点々が出たり、クモの巣のような細い糸がついていたり、しっかり水を与えているのに元気がない…そんな症状に悩んだ経験はありませんか。 私自身、部屋でハダニの発生…
観葉植物や庭木の葉に白い点々が出たり、クモの巣のような細い糸がついていたり、しっかり水を与えているのに元気がない…そんな症状に悩んだ経験はありませんか。 私自身、部屋でハダニの発生… -
観葉植物の葉が落ちるのはSOSサイン!復活の秘訣とNG習慣を大公開
 最近、買ったばかりの観葉植物の葉が次々と落ちて焦っていませんか?「葉が落ちるのは病気?」と不安になる気持ち、よくわかります。 実は私もオフィスでシェフレラ(カポック)の葉が突然ポロ…
最近、買ったばかりの観葉植物の葉が次々と落ちて焦っていませんか?「葉が落ちるのは病気?」と不安になる気持ち、よくわかります。 実は私もオフィスでシェフレラ(カポック)の葉が突然ポロ… -
徒長する前に防ぐ!観葉植物の成長をコントロールする簡単な日常ケア習慣
 「最近なんだかヒョロヒョロしてきた」「葉の間がスカスカで元気がない」と感じて、不安な気持ちになっていませんか? せっかくお気に入りの一鉢を迎え入れたのに、数ヶ月で形が崩れてしまうの…
「最近なんだかヒョロヒョロしてきた」「葉の間がスカスカで元気がない」と感じて、不安な気持ちになっていませんか? せっかくお気に入りの一鉢を迎え入れたのに、数ヶ月で形が崩れてしまうの…
新着記事
- オフィスの休憩室をカフェ風にするメリットと導入アイデアを解説!
 オフィスにおけるカフェ風の休憩室の定義やメリット、注目される理由、導入時に取り入れたいアイデアを分かりやすく解説します。生産性が高まるオフィス休憩室をつくりたい方は参考にしてくだ…
オフィスにおけるカフェ風の休憩室の定義やメリット、注目される理由、導入時に取り入れたいアイデアを分かりやすく解説します。生産性が高まるオフィス休憩室をつくりたい方は参考にしてくだ… - オフィスのリフレッシュスペースとは?メリットと作り方のポイントを紹介
 リフレッシュスペースは、従業員が心身を整え、仕事の効率や満足度を高めるための重要な空間です。リフレッシュスペースの必要性や設計時に押さえたいポイントを解説します。
リフレッシュスペースは、従業員が心身を整え、仕事の効率や満足度を高めるための重要な空間です。リフレッシュスペースの必要性や設計時に押さえたいポイントを解説します。 - 徒長する前に防ぐ!観葉植物の成長をコントロールする簡単な日常ケア習慣
 「最近なんだかヒョロヒョロしてきた」「葉の間がスカスカで元気がない」と感じて、不安な気持ちになっていませんか? せっかくお気に入りの一鉢を迎え入れたのに、数ヶ月で形が崩れてしまうの…
「最近なんだかヒョロヒョロしてきた」「葉の間がスカスカで元気がない」と感じて、不安な気持ちになっていませんか? せっかくお気に入りの一鉢を迎え入れたのに、数ヶ月で形が崩れてしまうの… - オフィスでの観葉植物のレイアウト8選!おしゃれに見せるコツも紹介
 当記事では、オフィスに観葉植物を取り入れる際のレイアウトアイデアや、観葉植物をおしゃれに配置するコツを紹介します。
当記事では、オフィスに観葉植物を取り入れる際のレイアウトアイデアや、観葉植物をおしゃれに配置するコツを紹介します。
法人のお客様には
グリーンレンタルを
無料でお試しいただけます。
『GOOD GREEN』は、全ての施設に最高のサービスを提供します。
観葉植物のレンタルが初めての方や、従来のサービスに不満がある方には、トライアル期間中無料でご利用いただけます。満足いただけない場合は料金を頂きません。植物が枯れた場合も無料で交換いたします。
ぜひ一度、プロのコーディネートを含めてお試しください。