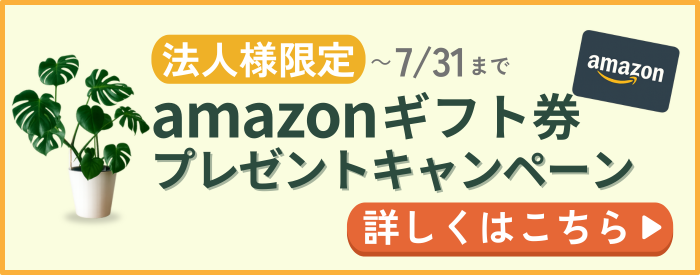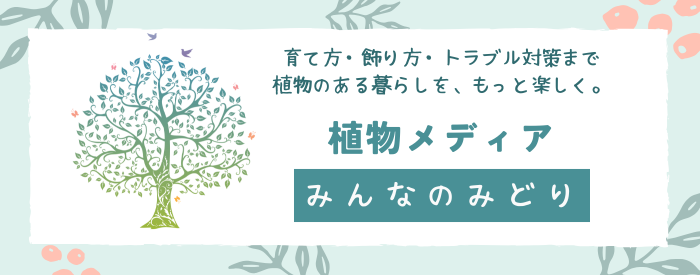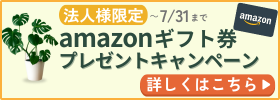法人のお客様には
グリーンレンタルを
無料でお試しいただけます。
『GOOD GREEN』は、全ての施設に最高のサービスを提供します。
観葉植物のレンタルが初めての方や、従来のサービスに不満がある方には、トライアル期間中無料でご利用いただけます。満足いただけない場合は料金を頂きません。植物が枯れた場合も無料で交換いたします。
ぜひ一度、プロのコーディネートを含めてお試しください。